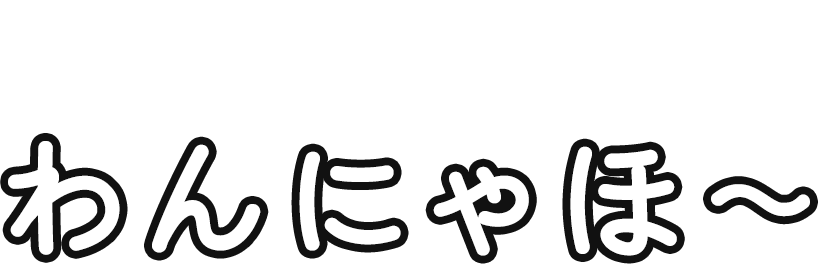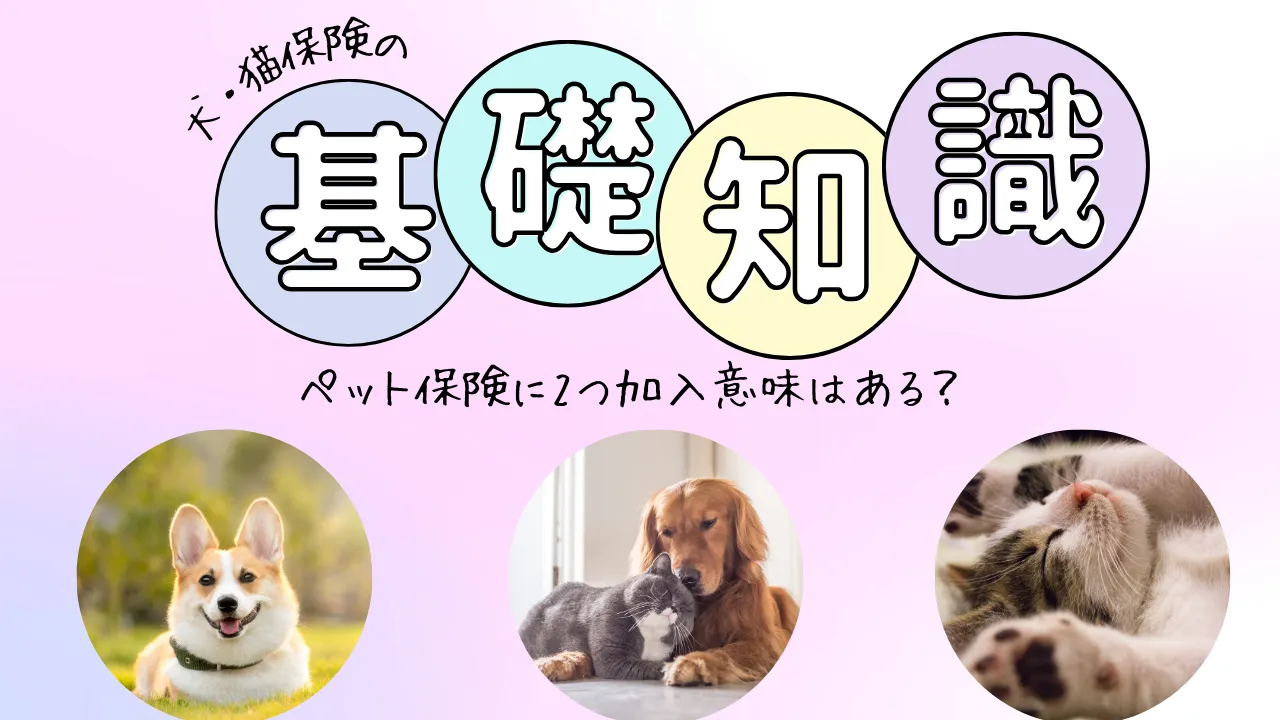
ペット保険に2つ加入する意味はある?
ペット保険の複数契約に
意味はある?
同じペットが複数のペット保険に加入することを「掛け持ち」といいます。
2つ、あるいは3つ以上掛け持ちすることで、A社では補償されない病気を補償してもらえたり、補償を100%にして自己負担を0円にしたりすることが可能です。
補償範囲が幅広くなる
ペットには、人間のような健康保険制度がありません。
治療費も明確に設定されているわけでなく、病院ごとに異なるため、病気やケガの治療が高額になりがちです。
加えて、ペット保険では、一般的に補償の限度金額や限度の回数が決められています。
このため、高額な手術を受ける場合や、何度も治療を受ける場合などに、補償が足りないと感じる場面があります。そんなときに保険を掛け持ちしていると、補償がより充実されるというメリットはあります。
2社以上の保険に加入していれば、入院や手術にしっかりと備えることができます。
例えば、50%補償のペット保険にしか加入していなかった場合、治療費20,000円のうち、10,000円しか補償されません。
しかし、50%補償のペット保険に2つ加入していた場合は、A社から10,000円、B社から10,000円の補償を受けることができるのです。
無保険の期間を減らすことができる
一般的に、ペット保険には待機期間が設定されています。
待機期間とは、保険に加入してから補償が始まるまでの期間のこと。
加入したペットが本当に保険加入にふさわしい健康状態か、保険会社が確認するために設けられています。
待機期間は保険会社によって異なりますが、30日間というケースが多いようです。
注意したいのが、待機期間の間に病気を発症したりケガをしてしまったりしても、補償の対象にならない点です。
慢性的な病気の場合は、その後も保険が適用されず、治療費がすべて自己負担になってしまいます。(ただし、病気が完治し、再発した場合は補償対象範囲になります)
しかし、ペットショップやブリーダーなど動物取扱業者で契約できる保険の中には、加入当日から補償を受けられる商品があります。これらを掛け持ちすることで、無保険期間を0日にすることが可能です。
ちょっとしたメリットではありますが、このためだけに掛け持ちするというのは、あまりにももったいない感じです。
ペット保険に2つ加入する
ときの注意点
複数のペット保険に加入すると、その分毎月の保険料は高くなります。
しかもペット保険にはいわゆる「掛け捨て型」が多く、ほとんどの場合、支払った保険料は戻ってきません。
掛け持ちをする場合は、「負担した保険料」と「受けられる補償」のバランスを考えるのがおすすめです。
治療費の100%を超える補償はされない
さらに注意したいのが、実際にかかった治療費以上の補償はされない点です。
例えば、ペットの治療費として10万円かかった場合、「補償割合70%の保険に2つ入っているから、それぞれから7万円ずつ、合計14万円受け取れる」と考えるかもしれません。
しかし、補償されるのは請求された治療費の10万円分のみ。
複数の保険に加入していても、保険金が多くもらえたり、それで儲かったりすることはないので注意しましょう。
保険会社への告知が必要!
ペット保険を提供する会社によっては、掛け持ちを認めていない場合があります。
契約に違反して掛け持ちをすると、いざというとき保険金がもらえないかもしれないので注意しましょう。
また、ペット保険を掛け持ちする際は、必ず保険会社に告知しなくてはなりません。
新たに加入する会社に告知するのはもちろん、すでに加入している会社にも連絡しないと、告知義務違反として補償を受けられなかったり、最悪の場合、強制的に解約されたりする恐れがあります。
ペット保険に2つ加入するなら
どんな組み合わせがいい?
ペット保険を掛け持ちする場合、それぞれの商品の「足りないところ」を補えるように組み合わせるのがおすすめです。
例えば、「リスクに広く備えたいが保険料はできるだけ抑えたい」という方は、「フルカバー型(通院も補償される保険)」と「入院・手術特化型」の2つの保険を掛け持ちするのがおすすめ。
「フルカバー型」+「フルカバー型」よりも、重複する補償を減らしつつ、安心を手に入れることが可能です。
「とにかく自己負担を0にしたい」という方には、補償割合50%プランを2つ契約することで、補償割合を100%にすることができます。
ただし、ペット保険にはそれぞれ免責金額や補償内容などに違いがあるので、よく確認した上で契約を検討してみてください。
ペット保険のかけもち、
プロはどう見る?
ペット保険は掛け持ちした方がいいのか?ペット保険を扱う代理店の田伏さんにお伺いしました。
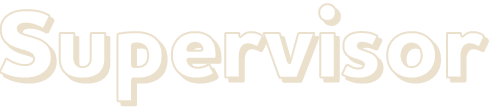



運営会社
ニッチトップのマーケティングと海外人材事業を軸にするZenken(ゼンケン)株式会社が制作・運営を行っています。
この「わんにゃほ〜」は、ペット保険の加入に悩む飼い主さんのために、保険のプロと獣医という、違う立場の専門家の意見をまとめ、飼い主さんたちが納得して判断ができるようなメディアを目指して制作いたしました。
少しでもみなさんの力になれることを願っています。