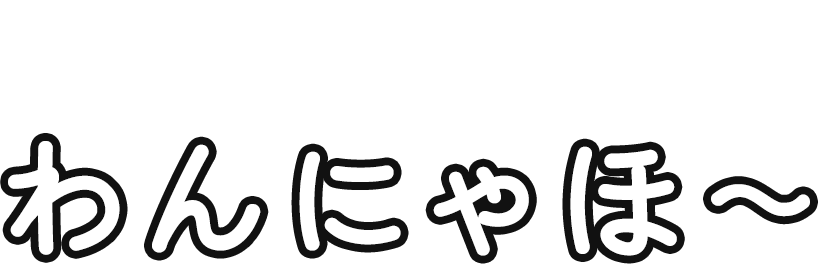ペットが怪我をさせたときに保険は使える?
ペットが他人やほかのペットを咬んで怪我をさせたり、他人のものを破壊してしまったりした場合、お詫びだけでなく、治療費、入院費、慰謝料といった損害賠償金の支払いが必要になる可能性があります。
損害賠償金は、数千円で済む場合もありますが、中には1,000万円など高額になることも…。
ここでは、そんな万が一に備える方法をご紹介します。
結論、ペット保険の賠償責任
特約つき
なら補償されます
ペットが人やほかの動物に怪我をさせてしまった場合でも、ペット保険の賠償責任特約に加入していれば、相手に治療費を支払ったり損害賠償に対応したりすることができます。
商品によって補償内容は異なりますが、1事故につき500万円までといった保険や、国内無制限・国外1億円、あるいは3億円を限度に保険金が支払われる保険などがあります。
また、保険会社によっては、対象となる事故について、飼い主にかわって示談交渉をしてくれる場合もあります。
保険料の相場は、年払いで1,000円~1,500円ほど。
月払いなら90円~140円と低価格で備えられるので、加入するのがおすすめです。
ただし、保険料によって補償額が大きく異なるので、内容をよく確認して選ぶようにしましょう。
参照元:アイペット損害保険株式会社 https://www.ipet-ins.com/faq/18156/、生活クラブ https://seikatsuclub-kyosai.coop/news/column/3729/
そのほかの保険も使えることも
ペット賠償責任特約のほか、個人賠償責任保険や火災保険・自動車保険の個人賠償責任特約、クレジットカード付帯の個人賠償責任保険などでも補償を受けられる場合があります。
例えば個人賠償責任保険なら、誤って人を傷つけたりものを壊したりした場合、1事故につき国内無制限・国外1億円や3億円を限度に保険金が支払われるものがあります。
また、火災保険や自動車保険の個人賠償責任特約は、1事故につき国内無制限・国外1億円、もしくは3億円までを補償してくれる商品が多いようです。
すでに加入している保険でカバーできているかもしれないので、保険証券や約款を確認してみるのがおすすめです。
保険に加入するときは
ここに注意!
万が一に備えて加入しておきたいペット賠償責任保険ですが、加入時には注意したいポイントがあります。
示談交渉まで対応してくれる保険が安心
飼い犬と他人・ほかのペットとのトラブルをスムーズに解決するためには、話し合いが不可欠です。
とはいえ、専門知識のない飼い主が示談交渉を進めるのは簡単ではないでしょう。
感情的に責められたり、高額な賠償金を請求されたりした場合の対応法が分からない、という方も多いのではないでしょうか。
そんなときに安心なのが、示談交渉サービスです。
保険のプロが、飼い主側の代理人として被害者側と話し合いを進めてくれます。
商品によってはサービスが付帯していないものもあるため、加入する前によく確認しておくと良いでしょう。
保険が重複していないか注意しよう
前述のように、ペットのトラブルには、火災保険・自動車保険の個人賠償責任特約・クレジットカード付帯の個人賠償責任保険などにも対応しています。
改めて保険に加入しなくても、すでに加入している場合があるので保険証券や約款を確認しましょう。
「いっぱい加入していれば、その分保険金がもらえるのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、個人賠償責任保険では実際にかかった費用のみが保険金として支払われます。
例えば、2つの保険に加入している人が、トラブルで100万円の賠償金が必要になった場合でも、各社から100万円ずつもらえるわけではありません。
一方の保険からだけ、もしくは各保険会社の保険金額から按分して合計100万円になるよう支払われます。
余計な保険料を支払わないよう、重複加入がないか注意することが必要です。
実は増えている、
犬による他害事故
「動物愛護管理行政事務提要(令和3年度版)」によると、犬による咬傷事故(咬みつき事故)の件数は、2010年~2019年までは4,100件~4,400件ほどでした。
しかし、2020年には4,600件台と大きく増加しています。
しかも、咬みつきを行った犬のうち9割以上は飼い犬で、ノーリードでの散歩、リードが長すぎた、飼い犬を制御できなくなってしまった、なでられて驚いて咬んでしまった、など原因はさまざまです。
中には死亡事故に発展してしまった、痛ましい例もあります。これだけ咬みつき事故が起きている以上、「自分の犬は絶対大丈夫」とは言い切れないのではないでしょうか。
飼い犬がほかの人やペットを
咬んでしまったときに
発生する責任
飼い犬がほかの人やペットを咬んでしまった場合、飼い主には民事責任だけでなく、刑事責任が発生します。
民事責任とは、他人(ペット)に加えた損害を賠償する責任のことです。
治療費に加え、通院交通費や休業損害、慰謝料、逸失利益、衣類などの被害に対する弁償を行わなければなりません。
もし相手が重傷を負って、大きな傷跡や麻痺などの後遺傷害が残った場合は、後遺傷害慰謝料も請求される可能性があります。
刑事責任とは、法律を犯したことで国家から刑罰を受ける責任のこと。
相手に過失傷害罪で訴えられ、罪が成立した場合は、30万円以下の罰金または科料に処せられます。
咬んでしまったらすぐ対応するべきこと
飼い犬がほかの人や動物に怪我を負わせてしまったときには、誠意ある対応が不可欠です。
まず行いたいのが、謝罪と応急処置です。
怪我の手当を行い、必要であれば、病院へ行くか、救急車を呼びましょう。
この際、狂犬病ワクチンを受けた証明書を提示すれば、スムーズに治療を行うことができます。
地域の保健所への届け出も大切です。
飼い犬が他人を咬んでしまったら、翌日までに地域の保健所に届出をしなくてはなりません。
市によっては「市長に届け出る」と規定されている場合もありますが、実務上はお住まいの地域の福祉保健センター 生活衛生課で大丈夫です。
また、飼い犬が狂犬病やそのほかの感染症にかかっていないか、確認することも大切です。
検診終了後は検診証明書を発行してもらい、必要があれば届け出先に提出します。
獣医さんに聞きました!
ペットが怪我させる・
させられることって
よくありますか?
起こりうることです
動物病院で夜間救急に携わっているSoheyです。
怪我をさせる・させられるのは公園やドッグランでよくあるケース。
そして、悲しいことに噛んでしまった犬の飼い主さんは何故か逆切れしたりして、噛まれてしまった飼い主さんは泣き寝入り状態…となってしまうケースもそこそこ見受けられます。
その上で、怪我させられてしまったときに備えて、以下の2点を覚えておいてください。
①噛まれてしまった状況を覚えておく(一方的だったか、じゃれ合っていたのか、自分の愛犬が噛んでしまった犬にしつこくしすぎて逆襲されてしまったかなど)、②相手の飼い主さんと連絡先を交換しておく。
犬と犬同士では、どこを噛まれたかは、その場では全体像がわからないことが多く、動物病院を受診して、必要に応じてかなりの広範囲の毛刈りをしてやっと傷口の全貌がわかる、なんてことも多いので、「軽傷かな」と思わずに、受診をしてください。
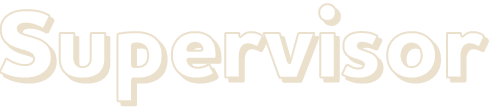



運営会社
ニッチトップのマーケティングと海外人材事業を軸にするZenken(ゼンケン)株式会社が制作・運営を行っています。
この「わんにゃほ〜」は、ペット保険の加入に悩む飼い主さんのために、保険のプロと獣医という、違う立場の専門家の意見をまとめ、飼い主さんたちが納得して判断ができるようなメディアを目指して制作いたしました。
少しでもみなさんの力になれることを願っています。