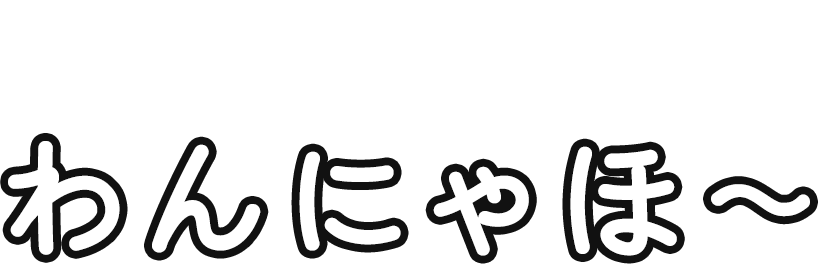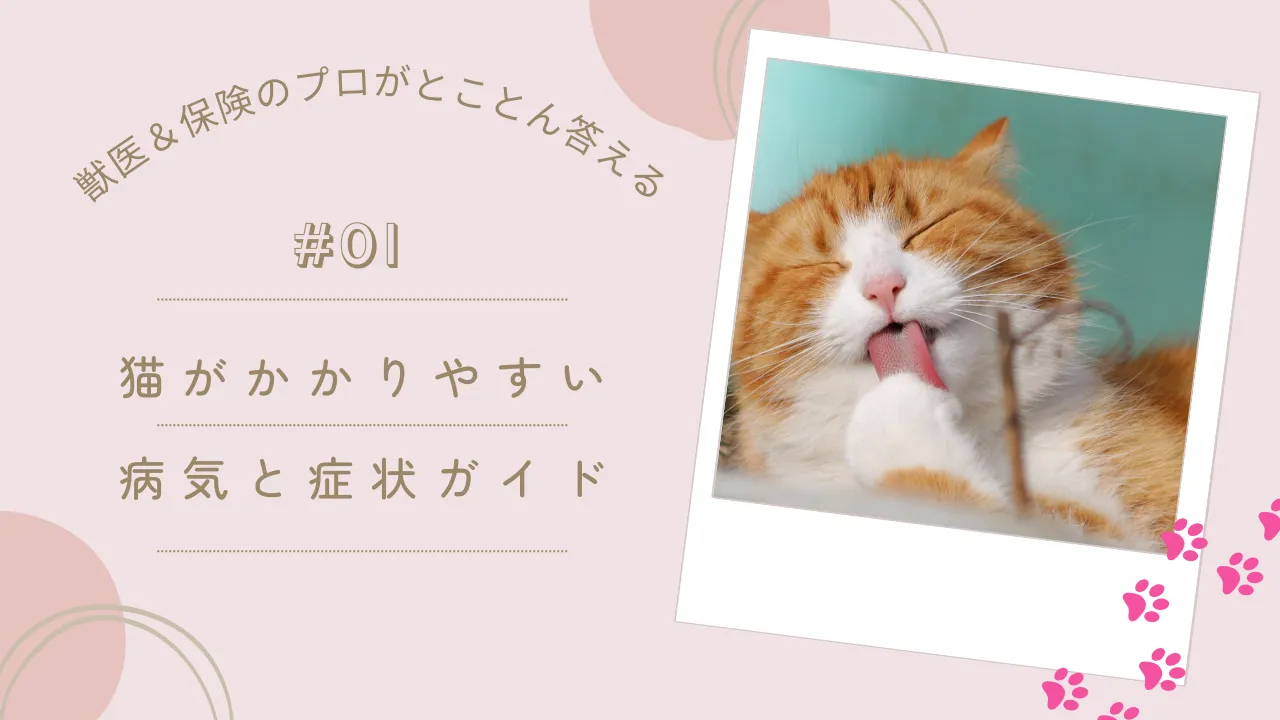
猫がかかりやすい病気と症状ガイド
猫がかかりやすい病気と症状、治療法
ここでは、猫がかかりやすい病気と症状、治療法についてご紹介します。
万が一の備えとして、情報を把握しておきましょう。
参照元:アニコム 家庭どうぶつ白書2017【PDF】 https://www.anicom-page.com/hakusho/book/pdf/book_201712_2.pdf、アニコム 家庭どうぶつ白書2019【PDF】 https://www.anicom-page.com/hakusho/book/pdf/book_201912_2.pdf、アニコム 家庭どうぶつ白書2021【PDF】 https://www.anicom-page.com/hakusho/book/pdf/book_202112.pdf
獣医さんに
聞きました!
飼い主様は、
保険加入を
おすすめします
個人的には1歳半から2歳くらいまでは保険に加入しておくことをおすすめします。
この期間は誤食や骨折など、子猫が元気すぎるとか、飼い主様が飼育に慣れていないなどの理由でさまざまなトラブルに遭遇するリスクが高い時期だからです。
特に初めて猫を受け入れる飼い主様は、安心のために保険加入をおすすめします。
ブリーダーやペットショップから購入する純血種は、品種による先天性疾患のリスク(特に心疾患)には大きな偏りがあるので、くれぐれも注意してください。
10歳越えたあたりでホルモン疾患の懸念も急速に高まるので、最遅でも10歳前に加入しておくのが良いでしょう。
純血種ではない日本猫であっても、先天性疾患および高齢になると起こりやすい病気病態は純血種と同様に起こるので、10歳前後には加入しておきたいものです。
猫下部尿路疾患(膀胱炎)
猫下部尿路疾患とは、膀胱から尿道までの下部尿路で起こる、尿路結石や膀胱炎、尿道炎、尿路感染症、腫瘍などさまざまな病気や症状の総称です。
年齢を問わず、多くの猫がかかりますが、老猫になると、よりかかりやすくなります。
猫下部尿路疾患(膀胱炎)になりやすい猫種
膀胱炎は、被毛の長さや出身地(日本/外国)など関係なく、すべての猫種に発症するといわれています。
性別による差もほとんどないとされていますが、オスの方が尿道に結石や炎症産物がつまりやすいため、その診察の過程で膀胱炎も発見されやすいようです。
尿路結石は、ヒマラヤン、アメリカンショートヘアー、スコティッシュフォールドなどがかかりやすいようです。
猫下部尿路疾患(膀胱炎)治療費目安
細菌性膀胱炎の場合は、2週間ほどの抗生剤投与で治療が完了するため、治療費の目安は大体5,000~7,000円程度です。
尿石症(膀胱結石)の場合は手術が必要なため、10万円以上かかることがあるようです。
猫下部尿路疾患(膀胱炎)の症状
血尿、頻尿、決まった場所以外での排尿、失禁などです。
- トイレの回数が増えた
- トイレに入っている時間が長いわりに、尿量が少ない
- 排尿時に痛そうに鳴く
- 排尿後のトイレ砂の色が濃い
などの様子が見られたら、早めに動物病院を受診した方が良いでしょう。
原因と治療法
加齢やストレス、食事内容や肥満などが原因でかかるようです。
ただし、細菌性膀胱炎は、外陰部から尿道を伝って細菌が膀胱に侵入し、感染することによって起こります。
治療方法は病気や症状によって異なりますが、軽症の場合は注射や食事療法、内服薬で治まります。
ただし、尿路結石の場合は、手術や入院が必要になる場合があります。
重篤化している場合には、陰茎切除が必要になる場合もあるので注意が必要です。
予防法
とにかく「水分を摂らせる」ことが重要です。
ただし、家庭で飼われている猫はそもそもあまり水を飲まないため、水飲み場を複数設ける・ウォーターファウンテンタイプの水飲み器を用意する、猫用の栄養補助飲料を与えるなど工夫が必要かもしれません。
感染症
猫はさまざまな感染症にかかりやすいと言われています。
一口に感染症と言ってもその種類はさまざま。
猫かぜと呼ばれる「上部気道炎」、発熱や下痢、嘔吐などの症状が出る「猫汎白血球減少症」、「猫エイズ」と呼ばれ、免疫力を低下させる「猫免疫不全ウイルス感染症」、野外で飼育されている猫に多い「猫白血病ウイルス感染症(FeLV)」などがあります。
感染症になりやすい猫種
マンチカン、スコティッシュフォールドなど。
「猫コロナウイルス」の突然変異によって起こる「猫伝染性腹膜炎」や、「ヘモバルトネラ感染症」、「猫免疫不全ウイルス感染症」などに注意が必要です。
感染症の治療費目安
治療費は、感染症の種類やその重症度、受診する病院によって異なります。
例えば上部気道炎(猫かぜ)の場合、目安の診察料は約1,000円、1週間分の薬代で5,000~1万円。
血液検査やレントゲン検査をする場合はプラス1万円前後です。
感染症の症状
こちらも、感染症の種類によって症状が異なります。
主な感染症と症状は以下の通りです。
- 上部気道炎:鼻水・くしゃみ・鼻づまりなどのほか、結膜炎・目やに・涙目・まぶたの腫れ
- 猫汎白血球減少症:発熱、下痢、食欲不振、嘔吐など
- 猫免疫不全ウイルス感染症(FIV):発熱、下痢、リンパ節種の肥大、体重の減少、貧血、歯肉口内炎、上部気道炎など
- 猫白血病ウイルス感染症(FeLV):発熱、貧血、リンパ腫、白血病、歯肉口内炎など
原因と治療法
主に、感染している猫の排泄物や唾液、目やにや涙などから感染します。
治療法は、抗生剤や抗炎症剤など薬を投与する内科治療が中心です。
予防法
ワクチンを接種することで予防効果を期待できるものがあります。
有効な治療方法がなく、発症のメカニズムも解明されていない「猫伝染性腹膜炎」を予防する場合は、なるべくほかの猫との接触を避け、室内飼育を徹底することが大切です。
胃炎・胃腸炎・腸炎
胃や腸などの消化器の粘膜が炎症を起こしている状態を言います。
人間と同じように、猫もかかりやすい病気です。
胃炎・胃腸炎・腸炎になりやすい猫種
年齢や猫種に関係なく、どの猫でもかかる可能性があります。
胃炎・胃腸炎・腸炎の治療費目安
治療費は、症状の重さや治療方法、病院などによって異なります。
一般的な治療(皮下注射、投薬、食事療法)を行う場合、5,000円~2万円ほどかかるようです。
入院をした場合は、4万円程度かかるケースもあります。
胃炎・胃腸炎・腸炎の症状
吐き気や下痢、食欲低下などです。
ひどい場合には嘔吐と下痢による脱水症状を起こすこともあります。
原因と治療法
食事や薬物の影響、ストレス、感染症や寄生虫、異物誤飲など原因はさまざまです。
毛が長い猫は、毛づくろいのときに飲み込んだ毛が消化管にたまってしまい、胃腸炎や胃炎を引き起こすことがあるようです。
軽症の場合は自然に治ることもありますが、複数回症状が見られる場合や悪化している場合は、注射や皮下点滴で治療します。
予防法
毛が長い猫は、こまめにブラッシングをするようにしましょう。
また、消化に悪そうなものや食べ慣れないものは与えない、与える場合は少量にするといった配慮が必要です。
誤飲を防ぐためには、観葉植物やおもちゃ・食べ物などを出しっ放しにしないことも大切です。
また、定期的な駆虫やワクチン接種を行い、ウイルス感染を防ぐのもおすすめです。
腎臓病
腎臓病は、高齢の猫に多くみられる病気です。
腎臓が長い年月をかけて少しずつダメージを受け、機能低下することで起こります。
10歳前後ごろから発病の確率が上がり、15歳以上では半数〜8割ほどの猫がかかる可能性があります。
腎臓病になりやすい猫種
種類を問わずすべての猫に注意が必要ですが、 シャムやアビシニアン、ペルシャ、ソマリなどの品種は腎臓病にかかりやすいと言われています。
腎臓病の治療費目安
初期段階で発見することができ、食事療法などで対応できる場合は、あまり治療費はかかりません。
しかし、急性腎臓病などで通院や入院が必要な場合は、5~15万円ほどかかることもあるようです。
なお、慢性肝臓病を治療する場合には、長期にわたって治療が必要です。
入院費用や手術費用などのほかに、毎月数千円~数万円。
透析や再生医療を行う場合は、さらに治療費がかかります。
腎臓病の症状
初期症状は、水を飲む量が増える、おしっこの量が増える(多飲多尿)こと。
トイレで長い時間おしっこをしていたり、水を長い時間ペロペロなめたりすることで気がつく人が多いようです。
さらに進行すると、食欲不振や体重の減少、嘔吐、脱水や便秘などの症状などが出てきます。
重症化した場合は、けいれん発作や不整脈などがおこり、命に関わる状態になってしまいます。
原因と治療法
細菌やウイルスの感染による腎炎、外傷、薬物などによる中毒、心筋症やショックなどによる腎血流量の低下、免疫疾患などによる腎炎、結晶や結石などによる尿路の閉塞など、さまざまな原因があります。
治療方法は、食事療法、輸液、降圧剤や吸着剤などによる対処療法がメインです。
ただし最近では、薬の投与によって進行を遅らせる治療も始まっています。
予防法
日々の食事に配慮し、トイレの様子などを良くチェックしておきましょう。
ただし、腎臓病は症状がわかりにくく、気づかないうちに症状が進行する場合が多いため、定期検診を受けるのがおすすめです。
歯肉炎・歯肉口内炎
歯肉炎とは、歯肉が腫れたり、歯と歯肉の間から出血したり、膿が出たりする病気です。
歯肉口内炎は、口の粘膜(口腔粘膜)の炎症が原因でさまざまな症状を引き起こす病気です。
猫は歯肉口内炎にかかりやすいので、注意が必要です。
歯肉炎・歯肉口内炎になりやすい猫種
この種類だからということはなく、どの猫種でもかかる可能性があります。
歯肉炎・歯肉口内炎の治療費目安
歯肉炎・歯肉口内炎の治療費は高額です。
特に全身麻酔下で抜歯を行うと10万円~20万円ほどかかります。
歯肉炎・歯肉口内炎の症状
- 歯肉炎:歯茎が赤く腫れる、歯茎に炎症がある、歯と歯肉の間から出血する、膿が出る。進行すると、歯がぐらつき、歯が抜けることもあります。
- 歯肉口内炎:よだれを頻繁に垂らす、食欲不振、体重減少、口を気にして引っ掻く、餌を食べるときやあくびの際に痛そうにする、など。重度になると食欲が低下し、体重も減少します。
原因と治療法
歯肉炎の原因は、歯に付着した細菌や細菌が出す毒素などです。
歯肉口内炎は、細菌・ウイルスの口腔内の感染、免疫反応異常などと言われていますが、詳しい原因はわかっていません。
治療法としては、抗生剤、免疫抑制剤、ステロイド剤、インターフェロンの投与による内科治療と、抜歯による外科治療です。
完治を目指す場合は、歯をすべて抜いてしまうので、猫の体力も必要です。
予防法
家庭での定期的な歯磨きが効果的です。
歯磨きを嫌がる猫には、歯科予防用のおやつなどを与えたり、動物病院定期的にスケーリングを行ってもらったりするのがおすすめです。
甲状腺機能亢進症
甲状腺機能亢進症(こうじょうせんきのうこうしんしょう)とは、甲状腺ホルモンの過剰分泌によって起きる病気です。
8歳以上の高齢の猫に発症しやすいと言われています。
一度かかると完治することはなく、一生涯付き合っていかなければなりません。
甲状腺機能亢進症になりやすい猫種
かかりやすい猫種は特になく、高齢の猫はすべての猫種でかかる可能性があります。
甲状腺機能亢進症の治療費目安
治療費の目安は、1回の通院で2,000円~10,000円ほどです。
ただし、手術や入院が必要な場合は、数万円のかかる場合もあります。
甲状腺機能亢進症の症状
主な症状は、嘔吐、下痢、食欲不振、体重減少、多飲多尿などです。
原因と治療法
甲状腺機能亢進症の原因は、甲状腺が肥大し、甲状腺ホルモンを過剰分泌するためと言われています。
甲状腺が肥大する原因は、遺伝的な要因や食事、建築物の化学物質などさまざまです。
治療方法としては、食事療法、薬による内科療法、甲状腺摘出の外科療法などです。
予防法
残念ながら、いまだに予防法は知られていません。
定期的な検診で、早期発見・早期治療を目指しましょう。
子猫がかかりやすい病気
免疫が不十分な子猫は、病気になりやすい状態です。
体調不良にすぐに気づけるように、どんな病気にかかりやすいか、知っておきましょう。
感染症
猫伝染性鼻気管炎ウイルス感染症、猫カリシウイルス感染症、猫白血球減少症(猫伝染性腸炎)、猫白血病ウイルス感染症、猫クラミジア感染症、猫伝染性腹膜炎、ヘモバルトネラ感染症、猫免疫不全ウイルス感染症など
寄生虫
回虫、鉤(こう)虫、条虫、フィラリア、コクシジウムなど
猫の年齢別の死亡原因
(※)参照元:アニコム 家庭どうぶつ白書2012【PDF】 https://www.anicom-page.com/hakusho/book/pdf/book_202112_2_3.pdf
0歳
0歳の死亡原因で多いのは、全身性疾患と消化器系疾患です。
この2つが突出して多いため、特に注意が必要でしょう。
特に気をつけたいのが誤飲です。
0~1歳の発生率がほかの年齢と比べても非常に高いので、飼い主の見守りや配慮が求められます。
5歳
5歳の死亡原因では、泌尿器疾患が突出しています。
10歳
10歳の死亡原因の第1位も、腎臓病に代表される泌尿器疾患です。
次いで、全身性疾患と腫瘍が同じ15.1%で第2位。
第4位に消化器疾患、第5位に循環器疾患が続きます。
腫瘍は、皮膚や骨、眼、肺、心臓、内臓、脳などさまざまな場所に発生しますが、早期に発見できれば、完治や再発を防ぐことが可能です。
15歳
15歳の死亡原因でも、泌尿器疾患が突出しています。
特に慢性腎臓病(腎不全)は高齢の猫に多く、腎臓の機能が徐々にダメージを受けて低下する病気です。
次に多いのが全身性疾患、消化器疾患、腫瘍などです。
呼吸器疾患や循環器疾患などにも注意が必要です。
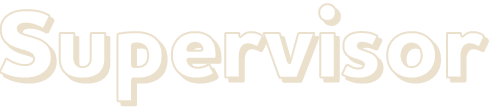



運営会社
ニッチトップのマーケティングと海外人材事業を軸にするZenken(ゼンケン)株式会社が制作・運営を行っています。
この「わんにゃほ〜」は、ペット保険の加入に悩む飼い主さんのために、保険のプロと獣医という、違う立場の専門家の意見をまとめ、飼い主さんたちが納得して判断ができるようなメディアを目指して制作いたしました。
少しでもみなさんの力になれることを願っています。